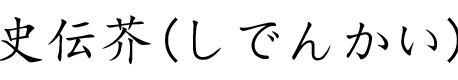授業力の向上方法
第一章:眠くなる授業と眠くならない授業の違い
予備校講師には「五者たれ」という格言があります。
…五者とは
「学者」(学び続ける人)
「医者」(生徒の悩みなどを把握(診断)する人)
「易者」(試験範囲などを予想する占い師)
「役者」(魅せる授業をする人)
「芸者」(興味を持たせ楽しませる人)
「これまでの経験から,それぞれ(1)(2)の先生の違いを考えてみましょう」
(1) 眠くなる授業…「学者」・「医者」タイプ(もちろん教員として必要な要素です)
→わかりにくい・淡々と喋る・メリハリがない、授業の合間に笑える要素・雑談がない
※史学科卒の先生にありがちな傾向=専門範囲を細かくやりすぎてしまい,時間がなくなる
→近現代・文化史まで高校の授業要領で必要なことを教えるのが先生方の仕事です。専門的な話は質問にきた生徒にのみするようにしましょう。「〇〇時代から急に早くなってほとんど説明されずに終わった」というのは生徒からよく聞くパターンの話ですが,全体の授業時間を計算して構成しましょう。ただし,あまり面白くない範囲を教える際,合間に雑談を入れるのは良いです(例えば文化史の授業音声ではカットしていますが,生徒の集中力が持たなくなりそうなタイミングを見計らって雑談を入れています)。
(2) 眠くならない授業…「役者」・「芸者」・「易者」タイプ
→わかりやすい・テンポが良い・メリハリがある、授業の合間に笑える要素・雑談を入れる
第二章:改善点を見つけ出すこと
中学・高校・大学の学生生活の中で10人以上など何人もの彼氏(彼女)を変えていた友達・知人はいませんでしたか?こういった人に共通しているのは「アイツのここがダメだった」とか,自分のことは省みずに他人のせいにしている点です。たとえ相手がどんなダメな男(女)であっても,それを選んだのは本人であり,相手を改善させる能力を持ち合わせていなかった本人にも問題点はあります。自分のどちらか片方に一方的に原因がある恋愛事例などはないと思っています。自分に人はいつまで経っても成長しません(不倫であっても不倫する人だけでなく,そんな相手を選んでしまった自分の見る目の無さを省みることが必要です)。
他にも,スポーツ選手でも「練習・試合での修正点などを見つける・試合に出られない理由を考える」選手は大成し,「監督のせいにする・試合に出られないで不貞腐れる」選手は大成しない傾向が強いですが。先生と授業も同じだと考えます。生徒が寝ていた場合,(部活動での疲労や家庭事情などもあるかもしれないのに)理由を問わずに怒る先生は成長しません。自身を向上させるためには,生徒が寝てしまう授業をしてしまった自分に落ち度はないか,と考えるようにしましょう。私自身は毎年卒業生に「わかりづらい内容や勉強しづらいページはなかったか?」と尋ねていますが,それを翌年度の授業の改善点につなげています。そのおかげか,近年は授業で寝るような生徒もおらず,テキストの改善点はむしろ自分自身で考えなくてはならない状況になりました(よりクオリティを上げられるページ構想があるので,今後も期待していただけると僥倖です)。
※生徒の生活リズム・時間帯・部活動・障害などでどうしても寝そうになってしまう生徒もいます。その際には例えば以下のように考えることができます。
(1) 先生自身…表に出さず怒らないで,「なぜ生徒が寝てしまったのだろう」と考えるようにしましょう
→寝てしまった・寝そうになっているタイミングがどの説明中か
※部活などで忙しく起きようとしているが眠そうになってしまう生徒もいます。
(2) 生徒への対応…意図的に寝ている生徒,寝そうになっている生徒で臨機応変に対応しましょう
Case1…意図的に寝ている生徒(1人だけ)
(1) あえて寝かせて放置→他の生徒が寝ていないのであれば,授業進行の妨げになるので放置
(2) 軽く起こしてあげる→すぐに起きれば問題なし(時間帯や体調もあるでしょう)
(3) 軽く起こしてあげる→怒らずに「何で寝ちゃったの?自分の授業つまらなかった?」
→もちろん寝てしまった生徒が悪いのですが,
極力自分が悪かったと思うように考えることで次回授業の改善に繋げられます。
Case2…意図的に寝ている生徒(複数人)
→この場合は授業に問題があると断言できるので,自分自身の改善に努めましょう。
第三章:眠くならない・面白い・楽しい授業を展開するには
「まずは“盗む(パクる)”こと(人聞きは悪いですが)」
芸人・タレント・先生(講師)などの喋りの上手い人の話し方を徹底的に盗みましょう。第一章のテンポが良い・メリハリがある・笑える要素など,私自身は芸人の一人喋り・漫才・コントを参考にしていました。
ただし,先生になりたての頃に,この要素をすでに兼ね備えている人はほぼいません。私自身も塾講師になった大学1~2年生の頃は習っていた予備校講師の丸パクリでしたし,初めは丸パクリで良いと思います。そこから,先生方の性格・個性からオリジナル性を出せるように3~4年かけていくと質の良い授業が展開できるでしょう(その頃を見越して金銭的負担が減るように,音声授業の更新をしないことができる利用規約にしています)。
第四章:飽きさせないようにするための発想
「私個人の授業展開なので…,出来る範囲で構わないから(『関白宣言(さだまさし)』より…古いわ!)」
(1) 覚え歌
天皇・将軍・内閣の順番は覚えにくいので、私は覚え歌10個で古代の天皇~近現代の内閣まで歌っています。
分国法・近世の手工業・文化史の仏教・儒学・学問は覚えにくい分野なので、私は覚え歌10個を歌っています。
※生徒からの「文化史の覚え歌が丸ごと出題されて合格できた」などの合格報告は嬉しいですね
(2) 一人芝居
人物が複数出てくる箇所は、説明するよりもストーリー調で人物のセリフを語っていく方が圧倒的にわかりやすいです。以下は難易度的に簡単な方から,
・向きを変える(右向き・左向きとそれぞれ変えてどちらの人物かわかるようにする)
・語尾を変える(~マロ・~でおじゃる・~でござる・方言(~やろ・~でごわす)・国の産物(~アル・~バーガー)
・お面をつける(作るのが面倒なので,私はやっていません)
・口調を変える(声の高さを変えるのは難易度が高いですが,落語家を参考にすると良いです)
(3) 紙芝居
マンガ『日本の歴史』のように“視覚的”印象を刷り込むことで,授業の面白さだけでなく生徒の記憶にも残ります。私自身は絵がド下手くそなので,アルバイトを雇って一枚5000円で描かせていましたが,今ならchatGPTを利用するのも一つの手ですね。
(4) BGM入り一人寸劇
これは高い演技力が求められるので,私のような劇団に所属していた方向けです(劇団ひとりが弟子にしてくれると“夢”に出てきたので,私は劇団ひとりの弟子です)。無料体験版の「南北朝時代」・「満州事変」などで演じているのですが,ご要望があれば演じてみたいですね。
(5) ボケ・ツッコミ
これも芸人の能力が求められるので,私のような劇団ひとりに師事していた方向けです(“夢”に出てきたので,私は劇団ひとりの弟子です)。
(6) 生徒の視点から方向(方角)を指示
脳の構造上非常に難易度が高いのですが,私は「左(右)に矢印出して」と説明する際に手の動きを生徒目線に合わせています。つまり,「左に矢印出して」と指示している際に私自身は「右手をそのまま右方向」に出しています(生徒視点から見ると「左方向」に見えます)。これは数年かけて練習したので,一朝一夕ではできないと思います。
第五章:私自身の経験を踏まえて全時代・全文化を消化する具体的時間の目安
「某予備校での授業時間(文化史含めて84時間)」
Case1.授業人気が高い予備校講師の手法=“端折る”(言葉を悪く言えば手口)
①一部の簡単な箇所は語句をcheckするだけで“誤魔化す”
→本当は時間をかければ説明できるが,授業時間の関係上あえて“端折る”
②難解な内容に時間をかけて説明し,残りの部分は端折ってプリントなどの補足で読ませる
→残りを端折ってプリントで補足する場合,説明付きプリントを配布する
※私個人の授業スタイルは②型ですが,「授業解説資料」は授業以上のクオリティを目指しました
Case2.授業人気が普通・悪い予備校講師の手法=“頻度の指導”(言葉を悪く言えば手口)
①語句の頻度だけをcheckして内容の説明はしない
→途中で生徒も“頻度付きの『一問一答』を見ればわかる”ことに気づくので生徒数は減少していく
②流れ(因果関係)がわかりやすい部分を説明して,難解な内容は誤魔化す
→複雑になる2学期の近現代あたりから生徒も“わからない”ので最終的な授業満足度は低い
第六章:予備校に通う必要性のなくなる授業を展開する解決策
①難解な内容を「授業展開書」で理解した上で,授業でしっかりと解説する
→授業満足度を上げるため+興味を持たせ面白い内容を授業する
「難解な内容の例」
・土地制度史(律令体制の崩壊~荘園公領制→守護・地頭・惣領制→国人・守護大名・太閤検地)
・幕政改革~幕末(三大改革(丸暗記ではなく因果関係で繋がります)・幕末の動乱)
・近現代(明治維新・松方財政~寄生地主制の成立・産業革命・大正~昭和時代の全て)
→近現代で難解な内容は政治・経済だけでなく(産業革命・松方財政・金解禁・北伐・日中戦争など),
社会主義・社会民主主義・共産主義・無政府主義・国家社会主義・全体主義などの“思想”が重要です。
②単純な内容は「授業解説」を読ませて“端折る”
→授業時間の短さを補うため+つまらない箇所の解説を省く
「授業解説で省いている箇所」(学校だと定期テスト前の生徒にとってはありがたい教材になります)
・基本的に「授業解説」がある箇所はほとんど読ませて終わりです(戦後史は時間が間に合わない場合の保険)
→極論「旧石器時代~摂関政治」・「中世・近世の社会経済」など生徒個人でも勉強できますが,
初回授業からそれをやってしまうと学生の授業に対する信頼度が下がってしまうので,
私自身は以下のカリキュラム形式で全時代・全文化を消化しています。
<1学期(4月~7月前半)>
「旧石器・縄文時代」→授業します
「弥生時代」→授業解説を配って「授業解説資料」の有効性を示します
「古墳時代」→流れの繋がる「外交・文化」だけを授業し,“天皇の覚え歌”で生徒に安心感を与えます
「ヤマト政権の政治制度(氏姓制度)」・「古墳の変遷」は授業解説を配って終わりです
「飛鳥時代」→流れが繋がる内容なので授業します(授業解説がありますが)
「律令制度」→授業解説を配って終わりです
「奈良時代」→時間があるので“天皇の覚え歌”もワンセットにして授業します(授業解説がありますが)
「平安初期(桓武・嵯峨朝・東アジア外交)~中期(摂関政治)」→授業解説を配って終わりです
「土地制度(律令体制~荘園公領制)」→難解な内容で授業力が問われる箇所なので授業します
↓(以降は授業解説がある部分以外は基本的に授業します)
「織豊政権」→豊臣政権が難解な内容なので授業します
↓(夏期期間中の課題として「幕藩体制~近世の社会経済」授業解説を配っておきます)
<夏期(7月後半~8月)>
※「幕藩体制~近世の社会経済」を夏期講習中に自学自習させます。
「文化史(古代~近現代の全文化)」
私は夏期講習で通史と関係性のある“仏教・儒学”を授業で扱いますが,
受験間際に詰め込むのが最も効率的なので,11月から学習を進めるように『文化史講義録』を配布します。
※夏期講習での「文化史講座」は近現代まで一周していない中で「近現代の文化」を組み込んでいる非効率なカリキュラムなので,近現代の文化は「大正時代が終わったら文化史講義録を読むように」と指示を出したりしています(文化史は学校ごとのカリキュラムに合わせて各自調整してください)
<2学期(9月~12月)>
※全体像の「三大改革~太平洋戦争」→授業解説がある部分を除いて授業します
「三大改革」→一般的には丸暗記に終始しがちな分野ですが,授業力の見せ所なので授業します
「百姓一揆・藩政改革(19世紀)」→(面白い内容ではないので)授業解説を配って終わりです
「開国~幕末」→授業力の見せ所なので授業します
「明治維新」→(時間の都合上)授業解説を配って終わりですが,ここで「近現代の勉強法」を教えます
「明治初期の外交」→授業力の見せ所なので授業します
「殖産興業」→(面白い内容ではないので)授業解説を配って終わりです
※この辺りで「〇〇でもわかる政治学・経済学」を読ませておけば,授業展開は非常に楽になるだけでなく相当生徒の学力は向上します。
「自由民権運動」→授業力の見せ所なので授業します
「憲法の制定」→授業力の見せ所なので授業します
「議会政治」→(時間の都合上)授業解説を配って終わりです
「大陸進出・条約改正」→(面白い分野なので)授業します
「産業革命」→(時間の都合上)授業解説を配って終わりです
※授業をすることも可能ですが,授業解説のクオリティが非常に高いので生徒も満足してくれます
「労働運動・社会主義運動」→(時間の都合上)授業解説を配って終わりです
※時間があれば授業をしたいのですが,大正時代にはより複雑になる10近くの主義・思想を完全理解させる「神回授業(生徒からいただいた言葉です)」があるので,あえて授業解説で済ましています
「大正時代(桂園時代~第二次護憲運動)」→(面白い分野なので)授業します
「大正デモクラシー」→(面白い内容ではないので)授業解説を配って終わりです
※ただし,ここで上述した10近くの主義・思想を授業します
「昭和時代」→授業力の見せ所なので授業しますが,時間の都合上間に合わない箇所は授業解説を配ります
※「満州事変」や「金解禁」,「日中戦争」・「日米関係の悪化」などは難解な分野ですが,昭和時代は私自身も好きな時代であり,生徒から「神回授業」と言ってもらえる最も評判が良い分野なので自信をもっています
「現代史(戦後史)」→時間があれば授業をしますが,時間がない箇所は授業解説を配布します。